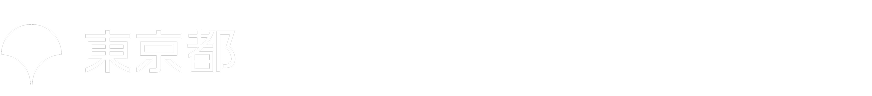ホーム » 降灰に備えるためには?

降灰に備えるためには?

降灰に備えるためには?
いつ起こるとも知れない、富士山噴火による降灰から身を守るためには、降灰の影響について理解し、日ごろから備えをしておくことが必要です。
このページでは、降灰に備えるためにどのような対策をすればよいか紹介していきます。
- 降灰によってどのような影響があるのか?については、「降灰による影響とは?」をご覧ください。
動画で知ろう・学ぼう
降灰に備えよう

ここからは、降灰前、降灰中、降灰後、平時からの主な対応について紹介しています。
降灰前後
富士山が噴火した場合、風向などにもよりますが、2時間程度で火山灰が東京まで到達する可能性があります。
富士山の火山活動が高まったり、噴火した場合は、降灰に備えて最新の情報を収集することが重要です。

- 情報収集
- 噴火の可能性が高まったり、噴火が発生すると、気象庁から降灰に関する情報などが発表されます。
- 災害時はデマや不確かな情報が拡散されやすいため、惑わされることがないように、気象庁や自治体などの、信頼性の高い情報源から情報を収集しましょう。
【気象庁が発表する主な火山防災情報】
降灰予報
- 噴火後に、どこに、どれだけの量の火山灰が降るかについて気象庁が発表する情報です。 活動が活発化している火山では、もしも今日、噴火が起こるとしたら、この範囲に降灰があります、という事前の情報も発表しています。
噴火の可能性が高くなっている火山では、噴火していなくても3時間おきに「降灰予報(定時)」を発表して、もし噴火したらどこまで火山灰が飛ぶかをお知らせしています。
火山が噴火したら、5~10分くらいで「降灰予報(速報)」を発表します。
その後、20分~30分くらいで「降灰予報(詳細)」を発表して、6時間先までの詳しい予想をお知らせします。
噴火警報・予報
- 生命に危険をおよぼす火山現象の発生やその拡大が予想される場合に「警戒が必要な範囲」(生命に危険をおよぼす範囲)を明示して気象庁が発表する情報です。 「富士山」は噴火警戒レベルを運用している火山のため、噴火警戒レベルを付して発表されます。
- 火災に関する防災情報は「火山灰・火山防災情報に関する知識」をご覧ください。
降灰中
降灰中は、周囲の状況に応じた適切な対応が求められます。
影響を最小限に抑え、健康と安全を守るために、落ち着いて行動しましょう。

- 在宅避難
- 火山灰が降っている間は、できる限り外出せずに自宅に留まることが基本となります。 降灰が落ちつくまでは、できる限り外出は控えましょう。
- 家屋倒壊など命の危険がある場合は、避難が必要になる可能性があるため、行政の指示に従いましょう。
- 室内に入る前に、服や髪に付着した灰を払いましょう。

- 室内への火山灰侵入防止
- 窓やドアをしっかり閉め、火山灰の侵入を防ぎましょう。
- 火山灰の粒子はとても細かいので、タオルなどを使用して隙間を塞ぐことも有効です。
- 室外機にカバーをかけることで、室外機からの火山灰の侵入やエアコンの故障を防ぎましょう。

- 健康被害への対策(身体の保護)
目
- 火山灰が目に入らないようにゴーグル等で目を保護しましょう。
- 火山灰が目に入ったら、手でこすらず水で流しましょう。
- コンタクトレンズをつけている場合は、火山灰により角膜を傷つける恐れがあるため、外して眼鏡を使用しましょう。
呼吸器系
-
やむを得ず外出の必要がある場合は、顔への密着性が高いマスクで口と鼻を覆いましょう。
※長時間屋外で作業をする場合などは、産業用として認証されたマスク(DS2やN95等)が望ましい。 - マスクがない場合は、ハンカチ等で代用しましょう。
皮膚
- 肌が露出しないように、長袖・長ズボンを着用しましょう。
- 火山灰が付着しないように、傘をさして防護しましょう。

- 車の運転自粛
- 車の運転は火山灰による視界不良やスリップによる事故のリスクが高くなるため、極力控えましょう。

- 火山灰の除去
- 火山灰は雪と違って、自然と無くなることはありません。 宅地内に積もった火山灰は自治体等の指示に従い、住民が協力して除去するといった「共助」が大切です。
- 火山灰は水に濡れると固まりやすく、排水溝が詰まる恐れがあるので排水溝に流さないようにしましょう。
- ほうきや火山灰を入れる袋などの清掃用具を準備しておきましょう。
- 清掃を行う際には、マスク・ゴーグル・長袖長ズボンを着用して清掃をしましょう。
平時
降灰はいつ発生するかわかりません。
普段から適切な準備をしておくことで、突然の状況にも冷静に対応できます。
いざというときに困らないよう、日頃から備えを見直しておきましょう。

- 備蓄
- 火山灰に対する備えとして、ゴーグルやマスクなどの火山灰対策用品も準備しておきましょう。
- 電気・水道・交通網など、ライフラインが使えない非常事態を想定し、食料品や日用品を日頃から備蓄しておきましょう。
- 過去の噴火(1707年宝永噴火)では2週間も噴火が続いたため、可能な限り備蓄を行うことが大事です。食料品や日用品は最低3日、可能ならば7日分以上確保しよう。
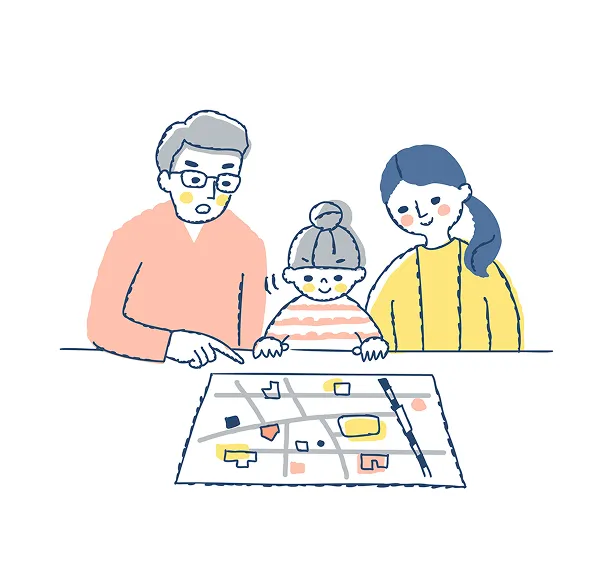
- その他
- 災害は家族が一緒にいるときに起こるとは限りません。別々の場所にいるときに、お互いの 安全を確かめるため、連絡先や連絡手段をあらかじめ話し合っておきましょう。
- いつも・いざというときにも役に立つ、東京都公式の防災アプリをダウンロードしておきましょう。
- 停電などにより電力が確保できない場合に備え、モバイルバッテリーやポータブル電源などといった電源を確保しておくことも大切です。

東京都の防災対策
富士山噴火に伴う降灰が起きても、交通やライフラインが長期間ストップすることがなく、都市活動を維持するため、東京都では、さまざまな対策を行っています。
詳細は「TOKYO強靭化プロジェクト~(東京都HP)」をご覧ください。